岩岡小学校スノードーム作り体験
親子で協力して作るペットボトルロケット...

教育員住岡さん
令和7年10月31日(金)、中種子町立岩岡小学校で、中種子町教育員住岡さんによるビーチコーミングで拾った材料でスノードーム作り体験が行われました。
今回の活動は、住岡さんが30年前から長浜海岸を歩き回って拾い集めた材料を使って、子供たちがスノードームを作る体験です。そして、ビーチコーミングのことも学びました。
その活動の模様を写真と動画を掲載しています。
中種子町の教育員の住岡さんです。住岡さんは、野間にお住まいで、30年前から長浜海岸を歩き回り、たくさんのものを拾い続けています。今回は、拾ったものを利用してスノードーム作りをします。写真1枚目です。
住岡さんがビーチコーミングを始めたきっかけは、海岸で緑のビンを拾ってどこから流れ着いたか知りたくなって興味を持つようになったそうです。海岸には、大きなクジラなども流れ着くこともあります。写真は、魚体から出てきたビニール袋です。写真2枚目です。

魚体から出てきたビニール
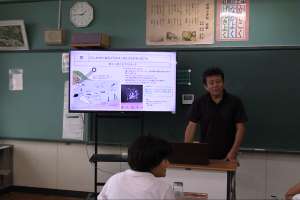
マイクロプラスチックのこと
写真3枚目は、海洋ごみの中で注目されているのがマイクロプラスチックゴミですね。種子島の海岸もそうですが、どこの海岸もゴミだらけです。それもなかなか分解されないプラスティックのゴミです。これが粉々になって、マイクロプラスチックになるわけエス。そして、いつかは、我々の体内に侵入します。
写真4枚目は、最近の傾向として、写真のような緑色をしたごみが多くなっているそうです。これは、人工芝です。家庭でも学校でも足ふきとして、どこにも設置されていますよね。靴底はきれいになっても海は汚れる一方ですね。

人工芝のゴミ

土台となるキャップを選ぶ
写真5枚目は、蓋のついた透明のビンの中にデザインします。蓋の裏にキャップを接着剤で固定して土台を作ります。そのキャップなどを選んでいる状況です。
写真6枚目は、土台となるキャップを固定するためにグルーガンで接着剤をつけている作業です。グルーガンは、プラスティックを高温で熱して接着させるものです。ボンドよりかは強度はないとされますが、早く固まるのが特徴とされます。、

グルーガンで接着する!

拾い集めた貝殻など
写真7枚目は、海岸で拾い集めた貝殻やサンゴなどです。そして、ロープの細かいものも使います。
写真8枚目は、蓋の裏側に土台を固定してそれにデザインします。すでに出来上がっているんでしょうか。シンプルに作り上げていましたね。

蓋の裏にデザインする

びんの中に入ったか確認する
写真9枚目は、土台の上にデザインしたものをビンの中に入れて確認しています。シンプルなほど飽きが来なくていいようですよ。
写真10枚目は、びんの中にラメ、ビーズなどを入れます。最後に液状の洗濯糊を7分目入れ、水を入れてふたを閉めれば完成です。

液状の洗濯糊を入れる

スノードームが完成!
海岸で拾ったものがきれいによみがえりました。いろいろ工夫すれば、ごみの再利用にもなります。とにかく、海を汚さないことが大事ですね。いつかは、小さなごみが私たちに帰ってきます。大変立派に出来上がっていました。写真11枚目です。
ウミガメ放流や留学制度については、中種子町立岩岡小学校(0997-27-9501)へお問い合わせてください。
2025年(令和7年)10月31日(金)、中種子町立岩岡小学校で行われた中種子町の教育員住岡さんによるビーチコーミングのこと、それを利用してスノードーム作りの模様をダイジェストで紹介しています。この動画の中には、海洋ごみのこと、種子島に漂着したのゴミのこと、マイクロプラスチックのこと、海流のこと、ビーチコーミングによって生まれた交流の紹介、スノードーム作りの様子、完成したスノードーム、児童の感想発表、お礼のあいさつの模様を収録しています。
なお、YouTubeでのアドレスとタイトルは次の通りです。
【種子島の学校活動:岩岡小学校ビーチコーミングで拾った材料で作るスノードーム作り体験!】
動画の二次元コードはこちら

- 【撮影場所】
- 鹿児島県熊毛郡中種子町立岩岡小学校
- 【撮影日時】
- 2025年10月31日(金)/13時31分〜15時09分
- 岩岡小学校令和7年度木育活動
- 岩岡小学校令和7年度秋の遠足
- 岩岡小学校うみがめ学習(2025年)
- 岩岡小学校開校記念日
- 岩岡小学校6年生を送る会・お別れ遠足(2025年)
- 岩岡小学校魚のさばき方教室(2025年)
- 岩岡小学校保健センターでのおやこ食育教室(2025年)
- 岩岡小学校もちつき大会(2025年)
- 第49回岩岡小学校親子駅伝大会
- 岩岡小学校助産師による命を守る安全教室
- 岩岡小学校オンライン授業スマホ・ネット安全教室
- 令和6年度岩岡小学校・校区合同秋季運動会
- 校内水泳大会・救急救命心肺蘇生AED研修(2024年)
- 岩岡小学校SDGs14海の豊かさを守ろう 海岸清掃活動(2024年)
- 岩岡小学校うみがめ学習
- 岩岡小学校開校記念日(2024年)
- 岩岡小学校令和6年度カヌー体験
- 岩岡小学校新1年生・留学生・転入生を迎える会(2024年)
- 岩岡小学校令和6年度入学式
- 岩岡小学校種子高生とのSDGs交流・黒糖づくり体験
- 岩岡小学校6年生を送る会・留学生とのお別れ会・お別れ遠足(2024年)
- 岩岡小学校考古学教室石器体験(2023年)
- 岩岡小学校出前授業木工製作体験(2023年)
- 令和5年度岩岡小学校・校区合同秋季運動会
- 岩岡小学校親子水ロケット作り体験(2023年)
- 岩岡小学校出前授業宇宙教室「宇宙食編」(2023年)〜
- 岩岡小学校保健センターでのおやこ食育教室(2023年)〜
- 岩岡小学校芸術鑑賞〜器楽「音の花束」〜
- 岩岡小学校令和5年度入学式
- 岩岡小学校黒糖伝承館での黒糖づくり体験
- 岩岡小学校もちつき大会(2023年)
- 岩岡小学校お茶とのふれあい事業(2022年)
- 岩岡小学校校内持久走大会(2022年)
- 岩岡小学校電気とエネルギー授業(2022年)
- 岩岡小学校海岸清掃(2022年)
- 岩岡小学校カヌー体験(2022年)
- 岩岡小学校令和4年度入学式
- 岩岡小学校種子高生とのSDGs交流・黒糖づくり体験
- 岩岡小学校6年生を送る会・留学生とのお別れ会・お別れ遠足(2022年)
- 岩岡小学校凧あげ・もちつき大会
- 岩岡小学校なわとび大会
- 岩岡小学校ボランティア認定証交付の表彰式
- 岩岡小学校JSPOフェアプレースクールオンライン授業
- 岩岡小学校ヤクルトウン知育授業
- 岩岡小学校宇宙飛行士大西さんとオンライン授業
- 岩岡小学校フラワーアレンジメント教室(2021年)
- 岩岡小学校校内持久走大会(2021年)
- 第47回岩岡小親子駅伝大会
- 岩岡小学校弁護士によるいじめ防止授業
- 岩岡小学校出前授業おかしの株式会社体験(2021年)
- 岩岡小学校学習発表会・PTA親子読書発表会(2021年)
- 岩岡小学校出前授業木工製作体験(2021年)
- 岩岡小学校ガンちゃん園整備・二宮金次郎像修復お披露目
- 岩岡小学校明治乳業主催骨について学ぶオンライン授業(2021年)
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験2021年
- 岩岡小学校青年海外協力隊OBと韓国留学生との交流会
- 岩岡小学校ウミガメ採卵(2021年)
- 岩岡小学校選挙の出前授業(2021年)
- 岩岡小学校カヌー体験(2021年)
- 岩岡小学校1年生・留学生を迎える会(2021年)
- 岩岡小学校うみがめ留学生の出発式(2021年)
- 岩岡小学校出前授業お菓子の株式会社体験(2021年)
- 岩岡小学校6年生を送る会・留学生とのお別れ会・お別れ遠足(2021年)
- 岩岡小学校学校介護について学ぼう!
- 岩岡小学校学習発表会・黒糖づくり体験
- 岩岡小学校鹿児島県ユニセフ協会出前授業
- 岩岡小学校第46回親子駅伝大会
- 岩岡小学校卒業生タイムカプセル開封!
- 岩岡小学校アレンジメントフラワー教室
- 岩岡小学校お茶とのふれあい事業
- 岩岡小学校親子読書発表会・持久走大会
- 岩岡小学校海外青年協力隊OBとの交流学習
- 岩岡小学校令和2年度秋季運動会
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験(2020年)
- 岩岡小学校魚のさばき方教室(2020年)
- 岩岡小学校春の一日遠足ウミガメ採卵(2020年)
- 岩岡小学校転出の先生とうみがめ留学生の出発式(2020年)
- 岩岡小学校人権作文発表会(2020年)
- 岩岡小学校岩岡まつり(2020年令和元年度)
- うみがめ留学21周年記念岩岡小学校中種子町PTA活動研究委嘱公開
- 岩岡小学校親子読書発表会(2019年)
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験2019年
- 残していきたいかごっま弁協会による公演(2019年)
- 校内水泳大会・救急救命心肺蘇生AED研修(2019年)
- 開校記念日地区敬老者とのふれあい活動(2019年)
- 春の一日遠足ウミガメ採卵(2019年)
- 岩岡小学校避難訓練(地震・津波)
- 岩岡小学校新一年生を迎える会
- 岩岡小学校6年生・留学生を送る会(2019年)
- 岩岡小学校人権作文発表会
- 岩岡小学校岩岡まつり(2019年平成30年度)
- 岩岡小学校剣道スポーツ少年団校内選手権大会(2018年)
- 岩岡小学校親子水ロケット作り体験2018年
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験2018年
- 岩岡小学校ピラティス教室・水泳大会・AED研修
- 岩岡小学校開校記念日(2018年)
- 岩岡小学校春の一日遠足ウミガメ採卵(2018年)
- 岩岡小学校避難訓練(地震・津波)
- 岩岡小学校留学生を迎える会
- 岩岡小学校岩岡まつり(2018年平成29年度)
- 岩岡小学校校内持久走大会
- 岩岡小学校たねがしま留学生安納芋収穫体験
- 岩岡小学校親子水ロケット作り体験
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験
- 岩岡小学校春の一日遠足ウミガメ採卵
- 岩岡小学校新一年生を迎える会
- 岩岡小学校平成29年度入学式
- 岩岡小学校親子駅伝大会・もちつき大会
- 岩岡小学校親子ふれあい給食
- 岩岡小学校保健センターでのおやこ食育教室
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験
- 岩岡小学校岩岡まつり
- 岩岡小学校出前授業木工製作体験
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験
- 岩岡小学校ウミガメ採卵
- 岩岡小学校ウミガメ放流体験
- 中種子町立岩岡小学校「ウミガメ放流」
- 中種子町岩岡「屋久津」 - 中種子町の地域情報
- 長浜海岸 - 中種子町の海岸